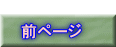
冬
臼引き・米搗き
ようやく外仕事が終わると、臼ひき(籾すり)と米搗き(精米)が行われた。
臼ひきは、機械一式をもって各戸を巡回する専門の人がいた。
 |
| 家庭用電力モーター |
発動機、籾すり機、調整機を雪橇で運んだ。山の斜面に家屋が点在している石黒では橇を使った運搬も容易な事ではなかった。
その後、家庭動力用モーターが普及すると、機械を購入し戸々で行うようになった。
 |
| 昭和中頃の動力精米器 |
作業小屋などなかった当時は、すべての作業を主に板張りのニ(屋内作業場)ワでおこなったため、脱穀やモミすり作業では座敷やミンジョの床まで白くなるほどのホコリがたった。
米搗きは、冬季間何度かに分けて行った。 上写真説明の分銅で調節する排出口があり、錘を動かし摺り具合を調節できる仕組みであった。しかし、錘を強くすると米が熱を持つため2~3回がけにして精白した。そのため排出口の下には精米箱を2つ用意して、一定の量になると箱を担ぎ上げて再投入した。筆者の経験ではこの作業は持ち上げる箱の重量を加減でき比較的に楽な仕事であった。
搗いた米は俵に入れて梁につるして保存したが、その後トタン製の大きな貯蔵タンクが普及した。このタンクは岡野町の高橋鍛(たん)工所で昭和30年に製作販売されたものであった。
 |
| 米貯蔵タンク〔高橋鍛工所〕 |
ちなみに、米搗きはその言葉通り、昭和の初めまでは臼の中に玄米を入れて杵で搗いた。この仕事を「センヅキ(千搗き)」と呼んだが、千回搗いてようやく白米となるという意味であろう。
資料→昔の米つきと飯米の保存
資料→ドウスとセンゴク・タテセン
資料→千づききね
資料-家庭動力設置の外線工事負担金請求書
出稼ぎ
雪の多い石黒では、日露戦争前後の頃から出稼ぎが行われ、昭和に入るとその数が徐々に増えた。まだ、出稼ぎが少ない頃は、出稼ぎに出発する人に餞別をやる風習もあり、帰ってきた人からはお茶のお返しがあった。
これを「江戸茶」と呼んだ。
さらに、昭和30年代の高度成長期に入ると、都会では労働力の需要が急速に高まった。一方家庭ではテレビ、洗濯機など生活の近代化に伴い現金支出が増え、それに対処するためには出稼ぎが必要であった。
資料→石黒の個数から見た出稼ぎの割合
資料→高柳町と石黒の出稼ぎ者の推移
11月に入ると農作業に決まりをつけて、冬囲いを済ませ、11月の半ばから翌年4月半ばごろまで出稼ぎに行く人が多かった。
しかし、失業保険制度との関連で6カ月間出稼ぎする人も多くなった。出稼ぎは、東京をはじめ、千葉、神奈川、埼玉と関東一円に及び職種は土建、酒造、工員などであった。
夫や長男が出稼ぎに出た後は、主に女性や老人が残って家を守った。大雪の冬には残された女性だけで20回にも及ぶ屋根の雪堀をしなければならなかった。
資料→炭鉱での出稼ぎ
資料→出稼ぎ者の皆様へ
資料→出稼ぎ者の皆様へ2
資料→出稼ぎと家を守る女衆
資料→出稼ぎ先より①
ワラすぐり・ワラたたき
ワラ仕事を始める前にしなければならない作業にワラスグリとワラタタキがあった。
ワラスグリは、ワラの根元の苞の部分を取り除く作業である。木製の簡単な道具(下写真)ですぐったり、臼を逆さにして千歯を取り付けてすぐったりした。2把のワラをすぐって束ねて1把とした。
 |
| 藁すぐリ具 |
このときに出たくずは、くず布団に入れたり、寝間に引き込んだりした。(日常の暮らし参照)
口に水を含んで霧を掛けて、ワラに少し水を含ませてしなやかにしてから叩くなど工夫した。どこの家の庭にもワラたたき専用の台石である「ジョウベイシ」があった。餅つき用の臼を伏せてその上で叩く家もあった。
ワラたたきを1人でする場合は、ヨコヅツを使い、片手でワラを回しながら叩いた。ワラがまんべんなく柔らかくなるまでには時間がかかり根気の要る仕事であった。
2人で叩く場合は、柄の短い掛け矢のようなワラ打ち専用の杵を用い、1人がたたき1人が回した。お互いに調子をとりながら行なわないと空打ちをしてしまうので気を配った。
ヌイゴはなかなか柔らかくならないので3回にわたって日をおいて叩いた。
また、叩いたワラは乾くと固くなる〔生返ると呼んだ〕のでムシロに包んでおき、使う時にもう一度軽く叩いた。
戦後、自家動力用モーター〔参考写真〕が普及するまではどこの家でも手で叩いた。
子どもの頃、冬の朝、3時頃にワラたたきのトントンという音で目が覚めたことを覚えている。
また、戦前から上石黒では数軒が共同で水車小屋を持ち、水車で藁たたきをしていた家もあった。
戦後に普及した自動ワラたたき機はモーターの力で2本の角材が上下してワラをたたくという方式の機械であったが、その後、ローラーにワラを通して潰す仕組みの機械も普及した。
資料→縄ない〔次項資料に同じ〕
資料→ワラクズ(イネの袴の部分)の利用
縄 な い
縄は農家にとって必需品あり、どこの家でも相当の量を冬季に綯(な)った。
縄には、機械縄とスベ縄があり、機械縄は足踏み機械で綯い、スベ縄やコデ縄は、手で綯った。
 スベ縄は、細く且つ緩やかな縒りで綯ったた縄でワラ細工に使い易いような綯い方であった。 スベ縄は、細く且つ緩やかな縒りで綯ったた縄でワラ細工に使い易いような綯い方であった。
その他、ハサ用のグミ縄(組縄)やモッコ縄、馬耕縄、荷縄、ヌイゴ縄、ダイモチ綱(つな)など必要に応じて様々な縄を綯った。
当時の縄ない機は、ペダルを踏みながら二つの差込口に数本の叩きワラを差し入れていく構造であった。タイミングを考えないと縄が太くなったり細くなったりする。
筆者の経験では一定の太さに綯うには足と手の動きのリズムを身につけることが肝要であると思った。
後に自家用の動力モーターが普及すると動力縄ない機になったが、仕様はほとんど足踏み機と同じであった。
資料→縄ない
わ ら 仕 事
わら仕事の内容は、ムシロ織り、カマス織り、俵編み、縄ない、ミノ、荷縄(シナの木の皮を混ぜるなど工夫した)、ジョゥリ(草履)、ワランジ、フカグツ、クツ、ワラボウシ、テゴ〔下写真〕作りなどであった。  わら仕事は、昼間だけではなくヨナベ仕事として、夕食後にも行われた。 わら仕事は、昼間だけではなくヨナベ仕事として、夕食後にも行われた。
家族全員が赤々と燃える囲炉裏の周りでそれぞれの仕事に精を出した。
男は主にワラたたきやミノや荷縄ない、女は俵編みやワラ草履づくり、年寄りは子どもを相棒ににイスシキ(石臼引き)などをした。
昼間の仕事は、機械や道具(下写真)を使った縄ないやムシロ織り、カマス織り、俵編みなどであり、機械を使う作業は主に板敷きのニワで行った。
余裕と技術のある者は、自家用に止まらず販売品も作って他家に売ることもした。とくに技術を要するミノやフカグツなど上手な人が作ったものは、使い勝手が良いばかりか 丈夫で見栄えも良く人気があった。 丈夫で見栄えも良く人気があった。
また、村の若い衆や親父連中が、宿を決め、五、六人が集まってワラ仕事をする慣習が昔からあった。
とくに、若い衆は宿にワラを持って集まり先輩から作り方を教えてもらったり、その他、四方山話をとおして様々な分野にわたって当時の社会を生きる術も学び合ったものであろう。
筆者が子どもの頃〔昭和20~26年ころ〕に、ワラ仕事宿になっている家の前を通ると楽しそうな賑やかな青年たちの声が聞こえ一種の羨望を感じたことを覚えている。
丈余(3m余)の雪に降り込められた古里で、モモヒキにヤマノノコを着て、叩き藁を手に宿に集まり、世間話をしながらりワラジやミノを作った遠い日を懐かしく思い出す人も多いだろう。
資料→ワラ仕事
資料→親たちの昔の暮らし
資料→アシナカ草履のつくりかた 動画
資料→スゲボウシの作り方 前篇 動画
資料→スゲボウシの作り方 後篇 動画
ムシロ織り、俵編み、カマス織り
ムシロは、今日の畳のように居間の敷物としてどこの家でも使われた。大抵の家では、年の暮れに新しいものと取り替えて正月を迎えた。
ムシロには、その他多くの使い道があった。
ゼンマイやカンピョウを干すときも表面に凹凸があるので風通しがよいため乾きが早かった。また、当時は、籾や米を入れるタテに使われたり、せんち(便所)などの戸の代わり使われる事もあった。
耐久性に優れ、座敷で敷き古したムシロも容易にすり切れなかったのでその後も様々な用途があった。当時の女の子は使い古しのムシロを庭に敷いてその上でママゴトなどをしていた。
資料→ムシロ織り
米俵は、主に供出米の入れ物として作られたが、編み方、重量などには厳しい規格があった。ワラはよく乾燥した一年前の物を使用し三つ編みにして、重量はサンベェシ(さんだわら)を入れて1貫300匁と決まっていた。俵編みは熟練した人でも1日8俵分が精一杯であったという。
その他、米俵はブリキ製の米タンクが普及するまでは、どこの家でも、飯米の保存にも使った。白米を俵に入れて座敷の梁につるして置き、必要なときに竹製のサシ〔米俵サシ〕を俵にさして米をミに取り出した。
また、カマスは、サツマイモなどのイモ類の収穫時の入れ物にしたり、柿の実を採って運ぶときにも使った。また、小豆ガラや豆ガラ(家畜の飼料)の保存にも使った。そのほか、大水の時の土嚢袋として使ったり、家によっては、飯米の保存にも使った。
戦時中にサツマイモやカボチャなどの供出が行われたときには、入れ物にこのカマスが使われた。
資料→供出米の俵編みの思い出
くんたん焼き
昭和30年(1955)代に保温折衷苗代が行われるようになると、くんたん焼きが盛んに行われるようになった。くんたん焼きとは籾殻を蒸し焼きにしたもので写真のようにして作った。 苗代での使用法は撒いた種籾の上を、くん炭で覆い保温の促進をしたものであるが、その後、その上をさらに油紙で覆う方法が普及した。その他、くん炭は田畑の肥料として使ったり、畔豆植えで豆を覆い隠し鳥害を防いだ。 苗代での使用法は撒いた種籾の上を、くん炭で覆い保温の促進をしたものであるが、その後、その上をさらに油紙で覆う方法が普及した。その他、くん炭は田畑の肥料として使ったり、畔豆植えで豆を覆い隠し鳥害を防いだ。
資料→くんたん焼き
資料→くんたん焼きと堅炭づくり
味噌煮・ 味噌玉づくり・仕込み
3月に入り雪の降り止んだ頃、どこの家でも味噌煮をした。味噌煮釜は、かまど付きの大層大きなもので3斗(54ℓ)の豆を一度に煮ることができた。(写真)
釜は村で共有して順番制で使った。豆は前日よく洗って水に漬けて置いてから煮た。石黒は雪が多いので、ニワ(土間)で煮る家が多かった。まだ雪のある寒い頃であるから、土間に隣接した馬屋の馬が気持ちよさそうに鼻を鳴らしていたものであった。
家の近くの通りまでただよう豆の煮える甘い香りにつられて集まった子どもたちは、煮た豆を少しずつもらって、針で糸を通して火棚につり下げて置いて少し乾いたところで食べた。
豆は3時間ほど煮てから手動の豆つぶし機にかけてつぶした。(手動の豆つぶし機が普及する前には新しいフカグツを履いてムシロの上で踏みつぶしたものだという)
つぶした豆は、子どもの頭ほどの味噌玉にして縄で十文字に縛って、居間の天井にぶら下げた。味噌玉は4月上旬に切り刻み、麹と塩を混ぜて巨大な味噌桶に仕込んだ。また、豆を煮た汁は捨てずに、煮詰めて「スイコ」として食用にしたり家畜の飼料として利用した。
資料→味噌煮1〔再出→衣食住-食〕
資料→味噌煮2〔再出→衣食住-食〕
いすしき(石臼ひき)
当時は、「タテセンノ下」と呼ばれた屑米のほとんどは粉にひいて粉餅やチャノコにして年間を通して食べた。凶作の年などは、籾殻をつけたまま粉に挽いたものだという。
その量は多い家では1石(180ℓ)にも達した。
これだけの量の粉を石臼で挽くのは並大抵のことではない。天井から下げた長い柄を付けた大型の石臼を仕立てて数人かがりで挽いた。
(日常の暮らし・食篇参照)
また、当時、上石黒に水車屋(集落の数軒で所有)が2軒あり(上石黒住居図参照)それを借りて製粉する家もあった。
家庭の石臼で挽いて作るものは、そば粉、きなこ、コウセン、だんご粉、とり粉、ナメコウセン(キビ)などであった。
家庭でのいすしき(石臼挽き)は、どこの家でも年寄りが子どもを相棒に、囲炉裏端で昔話など語りながら根気よくやった。
資料→大型石臼挽き
資料→石臼挽き
資料→大正時代の村の農業
資料→昭和初期の1年の暮らし

|




 スベ縄は、細く且つ緩やかな縒りで綯ったた縄でワラ細工に使い易いような綯い方であった。
スベ縄は、細く且つ緩やかな縒りで綯ったた縄でワラ細工に使い易いような綯い方であった。 わら仕事は、昼間だけではなくヨナベ仕事として、夕食後にも行われた。
わら仕事は、昼間だけではなくヨナベ仕事として、夕食後にも行われた。 丈夫で見栄えも良く人気があった。
丈夫で見栄えも良く人気があった。 苗代での使用法は撒いた種籾の上を、くん炭で覆い保温の促進をしたものであるが、その後、その上をさらに油紙で覆う方法が普及した。その他、くん炭は田畑の肥料として使ったり、畔豆植えで豆を覆い隠し鳥害を防いだ。
苗代での使用法は撒いた種籾の上を、くん炭で覆い保温の促進をしたものであるが、その後、その上をさらに油紙で覆う方法が普及した。その他、くん炭は田畑の肥料として使ったり、畔豆植えで豆を覆い隠し鳥害を防いだ。