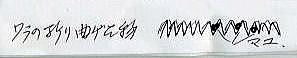| カイコ 田辺雄司 カイコは最初、ハキタテといって卵から孵ったばかりのケゴ(毛蚕)を買ってきて3、4軒で新聞紙の上に掻き落として分けたものでした。 ケゴには、桑の芽の部分の柔らかい葉を包丁で細かく切って与えました。少し大きくなると一枚ずつ葉をかいたものを与え、さらに大きくなると葉のついた枝を与えました。
カイコは蚕棚(かいこだな)と呼ぶ、幅3尺、長さ4尺ほどの5〜6段の棚で飼いました。棚は薄い板で枠を作り、その上に藁で編んだコモのようなものを敷いてその上にカイコを放し桑の葉を与えました。 カイコが小さいうちは、場所を取りませんでしたが大きく成長するにつれて、沢山の棚が必要になり、座敷、デー(客間)、板張りのニワと家中をカイコ棚が占領してしまいます。家の中はカイコの匂いが充満し、一斉に桑の葉を食べる音がまるで、さんさんと降る雨の音のように聞こえたものでした。  カイコは温度調節が大切であり、梅雨時の気温の低いときには火鉢に炭をおこしていくつも置いて調節したものでした。特にケゴの頃とマユをつくる頃の温度管理が大切でした。 私の家ではカイコの飼育は祖父が中心となってしておりましたが私たちも学校から帰るとカイコの餌の桑取りを手伝いました。雨の日には切ってきた桑の木を横穴の中に入れて水滴を落としてから与えました。 カイコは約1ヶ月間で4回脱皮をすると体が透き通るようになります。その前にマユを作らせるためのマブシ作りをするのでした。マブシは、
透き通ってきたカイコを拾い分ける仕事も大変忙しい仕事でした。当時は、素手でカイコを持つと良くないといわれ、タニウツギの枝で作った箸を使って拾い分けました。家族総動員の忙しい作業でした。
それから2日くらいで真っ白いマユが出来あがります。数日してマユかきといってマブシからマユを一つ一つはずしました。当時はまだ毛羽取り機もなかった時代でしたので、一つ一つ毛羽やゴミを取り除きました。 そして、きれいになったマユをマユ篭にいれて松代村に売りに行くのでした。松代村マユ市は毎年7月19〜20日の観音祭りの日に立ちました。 マユの買い付け商人は十日町や小出町から多数出ていましたのでマユ篭を背負って、買い取り値段を聞いてまわり一番高く買ってくれる商人を探して売ったものでした。 私も一度祖父に連れられて行きましたが、沢山の露天商が並びとても賑やかなものでした。 とくに、その頃が旬の桃の出店が沢山並んでいて、桃の香りが通りいっぱいに漂っていたことを今も懐かしく思い出します。 |