| 読書の思い出 大橋寿一郎 小学校に入学する前〔1944年頃〕の本についての記憶は、ぼんやりしたものばかりである。文字の読めない頃のことであるから絵を見て満足していたのであろう。 家にあった「一寸法師」や「桃太郎」など、数冊の昔話の絵本の挿絵が今も記憶の奥底に残っている。 昔話といえば、当時、祖母から「むかしあったってや」で始まる石黒に伝わる「昔話」をよく聞いたものである。 それは、「せいじょ」や「サルの嫁」や「えごの子」などの話だった。とくに化け物の出てくる怖い話「せいじょ」は好んで聞いたものだ。私の祖母が語り上手であったかどうか分らないが、いよいよ化け物の登場するクライマックスでは真に迫って、今にも座敷の暗闇から恐ろしい化け物があらわれるような気配を感じたものであった。 しかし、不思議な事に今、その話の筋を思い出そうとしても断片的な記憶ばかりでまとまった話にはならない。 これらの昔話をしてくれた祖母も三十数年前に亡くなった。聞き返すよすがもないが、できるならもう一度聞いてみたいものだ、などとかなわぬ事を思ったりする。 |
| 7才から9才ころになると学校の図書館の本を借りて読んだ。当時の小中学校併設校の図書室に備え付けられた本の冊数など知れたものであっただろうが、雑誌さえ買ってもらえなかった時代の子どもにとっては図書室は無限の宝庫のように思われた。書棚にずらりと並んだ少年少女世界文学全集など、背表紙を眺めるだけでわくわくしたものである。 低学年の頃に一番記憶に強く残っているのは「魔法の杖」という本であった。この物語は一人の少年がひょんなことから一本の杖を手に入れる。その杖は不思議な魔力を持っていて、振って呪文を唱えると望みの所へ一瞬のうちに行くことができるというものであった。読んでいるうちに、まるで自分が主人公の少年になったような気がしたものだ。私があまりに夢中に読んだせいか、この広い世の中にはこんな不思議な杖がほんとうに一本くらいあるに違いないと思ったほどだ。 心理学上ではこのような妄想がつのると杖を探しにあてどなくさまようこともあるともいわれるが、幸い私はそこまでには至らなかった。 |
10才から12歳には、読解力もつき図書館の本を友達と競って読んだものだった。とくに数十巻あった「少年少女世界文学全集」は読みごたえがあった。 「十二少年漂流記」の表紙の、いかだに乗って激流を下る少年たちの絵は今でも鮮明に思い出すことができる。「岩窟王」「ロビンソンクルーソー」「母を訪ねて三千里」「クオレ」「宝島」など、どれもこれも面白かったが特に感銘を受けたという本の記憶はない。今日の子どもがテレビアニメを見るように、ただ毎日楽しんでいたのであろう。 「十二少年漂流記」の表紙の、いかだに乗って激流を下る少年たちの絵は今でも鮮明に思い出すことができる。「岩窟王」「ロビンソンクルーソー」「母を訪ねて三千里」「クオレ」「宝島」など、どれもこれも面白かったが特に感銘を受けたという本の記憶はない。今日の子どもがテレビアニメを見るように、ただ毎日楽しんでいたのであろう。 |
| 中学生になると、学校の図書館の本では飽き足らず公民館の本を借りて読んだ。学校の帰りに役場の二階にあった閲覧室に入ると、一種、学校の図書館にはない雰囲気があった。それは未知の大人の世界への興味や期待であっただろうか。 また、この頃〔昭和28年ごろ〕から、日本の出版界も活力を取り戻してきた。笠信太郎の「ものの見方について」や伊藤整の「文学入門」などの斬新な評論や、三島由紀夫の「潮騒」や川端康成の「千羽鶴」などの文学作品の発表も話題となった。 しかし、本屋のなかった石黒で新刊書を手に入れることは容易ではなかった。そのため岩波文庫や創元文庫を郵便で取り寄せて読むことを始めたのもこのころであった。新聞や図書目録を見て、郵便局に行って代金と送料を振り込む。すると大抵は二週間ほどかかって郵送されてきた。本の届く日を指折り数えて待つのも楽しみなものであった。 |
| 初めて哲学に興味を持ったのも中学生の頃であった。二年生の時だと思うが、今は新潟市におられるТ先生が石黒中学校に赴任されて、私の家に下宿されることになった。新潟大学を卒業されたばかりの先生は学生服姿で現れ、沢山の蔵書を持ち込まれた。私は時々先生の部屋にお邪魔して文学や哲学のお話を聞くことに興味を持った。 あるとき先生が「君は自分が死んだらこの世の全てのものが消滅すると考えるか、それともこの世は今までどおり存在すると考えるか」と問われた。その時自分がどのように答えたかは覚えていないが、何か、人間の思考の深淵を覗いたような思いがしたことを忘れない。 |
高校の頃の私の読書の傾向は異常というか、まともでない面があったように思う。この頃に一番熱中して読んだのがニーチェであった。今でもそれらの本は書棚にあるが、どの本を開いてみてもやたらにサイドラインが 引いてあり、何度も繰り返し読んだらしく表紙も汚れている。とくに「反時代的考察」という本に共感した記憶がある。 引いてあり、何度も繰り返し読んだらしく表紙も汚れている。とくに「反時代的考察」という本に共感した記憶がある。ところが、今、私がニーチェについて何か言うことができるかというと何もいえない。のみならず、サイドラインの引かれた文章を読んでも共感はおろかその意味さえ分らないものが多いから不思議なくらいだ。私がニーチェに出会ったのは、柏崎の駅通りにあった古本屋でなんとなく手にした生田長江訳の「人間的なあまりにも人間的な」という一冊の本を通してであった。この本はニーチェの著作の多くがそうであるように、短章で著されていて独特の格調を持った文章であった。「いかなる教師もなし、思想家としては、我々はただ自己教育について語らねばならぬ」といった調子で書かれていた。おそらく、こういう文調と伝統的な価値を否定し新しい価値を求めた思想が多感な高校生の共感をよんだのであろう。 とにかく、低い次元であったにせよニーチェに心酔し「善悪の彼岸」「華やかな知恵」「権力への意思」「偶像の薄命」などむさぼるように読んだ。 |
しかし、ニーチェの世界から脱出する機会が訪れた。転機の一つは高校を卒業したことであつた。そこには、もはやニーチェに心酔し観念的な世界に遊ぶような雰囲気はなかった。生活での重要な関心事は山林の手入れや村の青年団活動をいかに進めるかというような事であった。もう一つの契機となったのは、フランスの哲学者モンテーニュを知った事である。ニーチェもモンテーニュを尊敬し「私は、この地上に永住せよとの使命を課せられてもモンテーニュと共であれば耐えていかれるであろう」と述べている。 ちょうどその頃、白水社から関根秀雄訳の「モンテーニュ全集」全四巻が発行された。私はそれを早速買って読んだ。背皮で天金の豪華な本であったが内容もそれにふさわしいものであった。「読者よ、これは、うそ偽りのない真っ正直な書物です」という書き出しで始まる随想録の世界はニーチェの世界とはまったく異なり、ゆったりとした悠々たる世界であった。私はたちまち、あたかも生きている人間の息吹を感じるような気持ちで「随想録」を夢中で読んだ。 |
| こうして私は、急にニーチェを読まなくなり、その代わりにモンテーニュをくり返し読むようになった。今でも随想録は時々本棚から取り出して開いたところから読み始める。それは私にとって、まるでずっと教えを受けてきた人を久方ぶりに訪ねてお話を聞くようにうれしいことだ。十数回もくり返し読んでいるから、どのあたりにどんなことが書いてあるかも大体見当が付く。また、探しているときが楽しい。 ページをめくっていると、二十歳のころの自分と出会うような気もする。当時は7月からお盆にかけて山林の下草刈をしたが、仕事の合間に木陰でよく読んだものだ。ホトトギスやウグイスの鳴き声を耳にしながら本を読んでいると、生きていることの幸せとはこういうものかと思うほどであった。 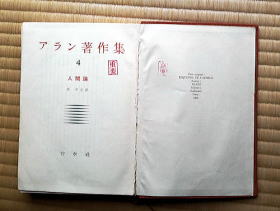 それから、この頃によく読んだものにアランがある。アランはモンテーニュの影響を深く受けた思想家であるが、「人間論」や「哲学入門」「幸福論」「情念について」などは、あくまで人間性を肯定する立場で、日常哲学が平易な文章で語られていた。 |
| 就職をしてからは仕事関係以外の読書は、そのほとんどがそれまでに読んだ本の中から選ばれたように思う。しかし、それは自分であれがよいこれがよいと選んだというより、本のほうが私に読みたいという気持ちを起こさせたと言う方があたっている。今考えてみるに、それらのほとんどが古典と呼ばれる書物であったように思う。 たしか、私が高校に入学した年であったと思うが、岩波書店が創立記念出版として「古典の読み方」という文庫本を出版したことがあった。無料であったので、もらって来て読んでみたが、文章を寄せた数人の有名人が口をそろえて古典を推奨している。当たり前のこととは承知しながらも何かつまらないように感じたことをおぼえている。 しかし、自分の読書を振り返ってみるとき、古典はその名の通り、古い時代から今日まで時代を超えて人々をひきつけるだけの内容を持った本であることは本当であると思う。 |
| 最後に、読書と人間形成とのかかわりについて考えてみたい。私は若い頃から己の人間形成の手段としての読書というものを考えた。つまり読書を通して自分が高められ、変容していくことを期待した。読書を続けていくと、いつか悟りが開けて己の妄念がぷっつり断ち切れる時が来ることを信じた。それこそ妄念と笑われそうな話であるがほんとうにそう信じていたのだから仕方がない。 しかしそのうち、このことに疑問を持つようになった。 それは、どんな優れた古典も自分の理解力程度にしか理解できないことに気づいたからだ。私の高校時代のニーチェのように、その時には著者の思想の真髄に触れたように思っていても、その実は自分の未熟な考えに都合のよい解釈をして得々としているということもある。 夏目漱石は鎌倉の円覚寺に参禅した時、かまどの火を焚きながら「碧眼録」を読んでいた僧に「本はあまり読むものではありません。いくら読んでも自分の修行程度しか分らぬから」と言われ、その見識に感服している。この僧の言葉の意味は、出家の修行の世界にだけ通用する事だとの反論もあるかもしれないが、自分はそうは思わない。なぜなら、我々は五十年生きて学び取った事を、未だ二十年しか生きていない者に言葉を尽くして伝えようとしてもなかなか伝わらないことを知っているからだ。このことは子を持つ親なら誰もが納得するであろう。 |
| 読書も先人との交わりと考えれば四十四歳の漱石が書いた作品は、読者もその年齢になれなければ十分には理解できないという事になる。私は昨年の暮れに十数年ぶりに漱石の「思い出す事など」を読んだ。これは、漱石が持病の胃潰瘍で吐血して人事不省におちいった、いわゆる「修善寺の大患」の記録であるが、前回読んだ時とは異なり強い感動を受けた。 勿論、仏教思想などについては若い人でも修行しだいで年齢を超えて理解できるものであるかも知れない。門外漢の自分には何ともいえない。 いづれにせよ、読書と人間形成の関わりは、一方が他方を高め、高められた方がまた他方を高めるという相互性があり、そこにこそ読書という行為の優れた一面があるのではないかと思う。 このように人間形成のための読書というものについて考えると、結局、それは優れた先達との対話であると思う。それも息の長い対話であると思う。一年や二年ではなく十年二十年と持続した対話が出来てこそ、真の読書というものであろう。そのためにはそれだけの長い年月にわたって対話のできる優れた書物と出会うことも必要になる。何世紀にもわたって読み継がれてきた古典というものは、その長い付き合いに応えることの出来る書物ということになろう。 |
| しかし、現代の学生や社会人が読書離れの傾向であることは否めない事実であり、読書はかつての役割を終える時代が到来しているかにさえ想われる。たしかに、コンピュータの普及とインターネットの充実により必要な情報はそこから入手できる。 しかし、人間形成のための読書となると少し異なることであると思う。これからインターネットがどのような進化を遂げるのか想像もつかないが、当分はパピルスの時代から数千年にわたって人間精神を啓発してきた書籍には太刀打ちできまい。 それにしても、今まで本が果たしてきた人間形成の一助としての役割を、インターネットがどのように果たす事ができるのかとても興味のあることでもある。 〔1997.2 二田小学校 職員研修誌〕 |