〔昭和の初めごろの暮らしのひとこま〕
〔前文略〕
いろりの火がとろとろ燃えている。夕餉の支度を終わった祖母が太目の薪を二本つぎたしてから、かぎつきさま〔自在鉤〕に鉄びんを掛け、夕方から弟をおぶっている私に、
「さあ、ぼぼ〔赤ん坊〕をおろせ」と、
背中から弟をおろし抱いてくれた。
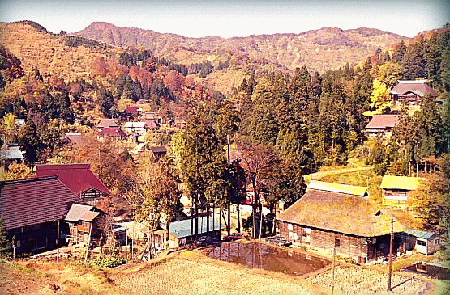 |
| 昭和40年代の上石黒集落 |
刈羽の屋根といわれている土地柄のせいか山の秋の夕ぐれば特に寒さが身にしむ。弟をおろした私はほっとした思いで、いろりの中の角に置いてある踏み台に両足を入れた。足を投げ出すと行儀がわるいと叱られるのを知っているので「ちびていね」と、祖母に許しをこうように小さな声でいうと、「ほら、湯が煮えたってきたぞ。じろに気をつけれ」
祖母はおきをかき出し、湯気を立てている鉄びんを片手でおろしその上にのせた。
弟をたたみの上にねかせてから、ほろ〔戸棚〕の前にある茶がまをかぎつきさまに掛けた。今までの窮屈から開放された弟は足をばたばたさせて喜んでいる。私の上と下の男の子が生後間もなく死んだので、この児は大切な後とりだからと殊更に可愛がられていた。
祖母に、
「ねい! ばばさ、ほらこのあいだの話のつづきはどうなったがん」とせがむ。
夕方のこのいろりは、私にとって祖母から昔ばなしをきけるたのしいひとときなのである。祖母といっても五十をでたばかりの元気者で、今考えるとばばさなんて呼ぶのは痛わしい年なのだが・・・・ 祖母は明治六年生まれで、文盲であるが伝承文学のかたりべで、つきることなく話をたくさん知っていた。祖父が山から上がってくるまで、祖母を独占しこうしているのが何より私にとってうれしい時間だった。
表の方から祖父の咳ばらいがきこえた。私がいろりからとび出し、がんぎの障子をあけた。「ああ、おじさだ」と、祖母に告げると、「さあ、ぼぼを預かってくれ」と、子守りをたのまれる。
これから判で押したようなことが、祖父と祖母の間に行われるのである。祖父は蓑を脱ぎ、とまぐちにあるみの掛けにかけ、かがんで草鞋をぬぐ。そのひもをきちんと揃えてそばのわらじかけにかける。それから敷石づたいに裏のたね〔池〕の方にまわる。この辺は雪が深いので、どこの家のまわりにも小さなたねがあり、その入口に平らな石が置かれた足洗い場がある。
祖父は足でぴちゃぴちゃと水を踏むようにして洗う。その間に祖母は沸かしてあった茶がまを提げて、みんじょ〔台所と風呂場〕に走り用意してあるたらいに湯を注ぎ待ちうけている。祖父は裏の入口から入ってきて、丁寧に顔を洗い、そのたらいの注ぎ湯で足を洗ってから座敷に上がってくる。
よこざに用意してあった祖父の綿入れを祖母はいろりにかざし、袖あぶりをする。そして心得たようにあったまった着物を祖父の背中から掛ける。祖父は三尺帯をくるりと前にまわし、どっかりとよこざに坐る。この場所は祖父のほかはお坊さん、本家さんと、我が家にとっての上客しか坐れないところである。
祖父は傍らにあるたばこ盆を引きよせてキセルに刻みたばこのなでしこを馴れた手つきで詰めてから、いろりにかざし火種をとり、「フーッ」と一服する。二度ほど祖父の鼻から煙が出ると、もう一度同じ動作をしたあと、ポンポンといろりの縁にキセルを叩き灰をおとす。祖母は立ち上がり茶道具を、ほろから出してきて、かかざに坐りお茶をいれ、くりぬき盆に載せて祖父の横におく。ゆっくりと一口、二口美味しそうにすする祖父。
こうしたことが秋の終り頃になると毎日目にする光景だった。何も言わないのに次から次へと、ことが運ばれてゆく。この、あ、うん、の呼吸に私は不思議な思いで見とれるのだった。〔後文略〕
柳橋孝著「あとには虫の声しげく」から抜粋
〔著者 柳橋孝 旧姓田辺 上石黒出身 川崎市在住〕

|